本日は、「感銘を受ける」という表現について、その意味や使い方を徹底的に解説してまいります。この言葉は、私たちが日常生活やビジネスシーン、さらには転職活動などさまざまな場面で目にすることが多いですが、実際に使うとなるとその正確な意味や適切な使い方に迷うこともあるでしょう。
今回の解説では、辞書的な意味を始め、具体的な使用例やビジネスシーンでの効果的な使い方、さらには類語や対義語についても詳しくご紹介いたします。
また、「感銘を受ける」の表現を豊かにするための豆知識もご用意しました。これらを通じて、この言葉の使い方やその持つ深い意味を理解し、実生活で効果的に活用できるようになっていただければと思います。それでは、具体的な内容に入っていきましょう。

「感銘を受ける」の意味と使い方を徹底解説
「感銘を受ける」とは?
日常生活で「感銘を受ける」という表現を耳にすることが多いですが、実際に使うとなると、その正確な意味や使い方に自信が持てない人も多いでしょう。「感銘を受ける」という言葉は、感動した際に使われることが一般的ですが、その使い方には注意が必要です。この言葉の意味を理解し、適切に使えるようになりましょう。
「感銘」とは?
「感銘」の意味を確認してみましょう。辞書で調べると次のように定義されています。
感銘/肝銘(かんめい)
忘れられないほど深く感じること。心に深く刻みつけて忘れないこと。
このように、「感銘を受ける」とは、忘れられないほどの感動を経験し、自分の考え方や生き方に大きな影響を与えるような深い感動を意味します。
「感銘」を「肝銘」と書いてもOK
「感銘」の漢字表記は、「肝銘」でも正しいとされています。どちらの表記も認められていますが、一般的には「感銘」がよく使われます。特にビジネスシーンでは、「感銘」を使うのが無難でしょう。
「感銘を受ける」の適切な使い方
「感銘を受ける」の使い方を例文とともに見ていきましょう。
日常での使い方
日常生活で「感銘を受ける」を使うシーンは多々あります。
例文:
・あの作家の作品に感銘を受けることが多かった
・環境問題に興味を持ったのは、この本に感銘を受けたからだ
このように、「感銘を受ける」はさまざまな表現に応用できます。「感銘を覚える」「感銘を与える」といった表現も覚えておくと便利です。
ビジネスシーンでの使い方
ビジネスシーンでは、「感銘を受ける」を使う際に丁寧な表現が求められます。
例文:
・社長のお言葉に、感銘を受けました
・お客様に対して丁寧に対応される先輩の姿を見て、感銘を受けました
ビジネスシーンでは、相手の仕事に対する姿勢や考え方に感動した場合に使われることが多いです。
転職活動での使い方
転職活動においても、「感銘を受ける」は頻繁に使用されます。エントリーシートや面接で、企業の事業内容や経営理念に対する感動を伝える際に使われます。
例文:
・御社の経営理念である「顧客第一主義」に強い感銘を受け、志望いたしました
・御社の会社説明会で、採用担当者の方が言われた言葉に強い感銘を受けました
転職活動でこの表現を使う場合、具体的にどの部分に感銘を受けたかを説明することが重要です。理由を丁寧に伝えることで、志望度や意欲を効果的にアピールできます。
「感銘を受ける」の類語と対義語
「感銘を受ける」の類語や対義語を見ていきましょう。これを知ることで、語彙力が向上し、表現の幅が広がります。
「感銘を受ける」の類語
「感銘を受ける」にはさまざまな意味があります。それぞれの意味に対応する類語を見てみましょう。
類語:強く感銘を受け、印象に残ること
・感動する
・強く印象に残る
・心打たれる
・目に焼き付く
・感動が押し寄せる
・魂が揺さぶられる
類語:強く思い、忘れないようにする
・心に刻む
・肝に銘じる
・忘れないようにする
・脳裏に刻み込む
・しっかりと記憶する
類語:鮮烈なイメージに衝撃を受けるさま
・印象に残る
・インパクトが強い
・目の覚めるような
これらの類語をシチュエーションに合わせて使い分けると、より豊かな表現が可能になります。
「感銘を受ける」の対義語と使用時の注意点
「感銘を受ける」の対義語
「感銘を受ける」という表現の反対の意味を持つ言葉を知っておくと、より多彩な表現が可能になります。「感銘を受ける」の対義語をいくつか挙げてみましょう。
対義語:
・無感動(心が動かされないこと)
・無関心(興味がない、関心を持たないこと)
・失望する(期待がはずれてがっかりすること)
・幻滅する(期待や憧れが現実と異なり、がっかりすること)
これらの言葉は、感動や強い印象を受けない状況を表す際に適しています。
「感銘を受ける」を使う際の注意点
「感銘を受ける」は非常にポジティブな意味合いを持つ言葉ですが、使用する際にはいくつかの注意点があります。適切に使うことで、言葉の効果を最大限に引き出すことができます。
1. ネガティブな文脈には不適切
「感銘を受ける」は、基本的にポジティブな感動を表現するための言葉です。そのため、ネガティブな出来事や感情には適していません。例えば、悲しい出来事や失望を表現する場合には、「感銘を受ける」を使わないようにしましょう。
例文:
誤った使い方:
・友人が事故に遭ったニュースを聞いて、感銘を受けた。
この場合、「衝撃を受けた」や「驚いた」といった表現の方が適切です。
2. 日常の些細な感動には適さない
「感銘を受ける」は、人生や考え方に大きな影響を与えるような深い感動を表すため、日常のちょっとした出来事にはあまり適していません。日常の些細な感動には、より軽い表現を使う方が自然です。
例文:
適切な使い方:
・友人の親切な行動に感動した。
このように、「感動した」や「嬉しかった」といった表現を使うと、日常の感動を自然に表現できます。
3. 多用は避ける
「感銘を受ける」をあまり頻繁に使用すると、その効果が薄れてしまいます。特にビジネスシーンや転職活動で多用することは避けるべきです。言葉の重みを保つためには、特別な場面で使うようにしましょう。
例文:
不適切な使い方:
・毎日のミーティングで、上司の言葉に感銘を受ける。
この場合、「感心する」や「参考にする」といった表現がより適しています。
「感銘を受ける」を具体的に伝える方法
「感銘を受ける」を使う際には、具体的にどの部分に感銘を受けたのかを詳しく説明することが大切です。具体的な理由を述べることで、相手に自分の感動をよりリアルに伝えることができます。
例文:
・社長の「顧客第一主義」という経営理念に深く感銘を受けました。その理念が実際の業務にどのように反映されているのか、具体的なエピソードを聞くことで、自分の価値観と一致することを強く感じました。
このように、具体的なエピソードや理由を付け加えることで、感銘を受けた理由が明確になり、相手にも伝わりやすくなります。
「感銘を受ける」の具体的な使用例と効果的な使い方
具体的な使用例
「感銘を受ける」は、感動や深い印象を表現するための重要な言葉です。ここでは、さまざまなシチュエーションにおける具体的な使用例を見ていきましょう。
日常生活での使用例
日常生活において「感銘を受ける」を使うシーンは多岐にわたります。例えば、芸術や文学作品に触れたときや、他人の行動に感動したときなどが挙げられます。
例文:
・この映画のラストシーンには本当に感銘を受けました。
・彼の誠実な対応に感銘を受けて、私も見習おうと思いました。
これらの例文では、「感銘を受ける」を使うことで、深く心に残る感動を表現しています。
ビジネスシーンでの使用例
ビジネスシーンでは、上司や同僚の行動、企業の理念やビジョンに感銘を受けた場合に使うことが多いです。具体的な例を見てみましょう。
例文:
・上司のリーダーシップに感銘を受け、私もその姿勢を見習いたいと思います。
・このプロジェクトの成功に向けたチームの一体感に感銘を受けました。
ビジネスシーンでは、相手の行動や考え方に感動したことを伝えることで、感謝や敬意を示すことができます。
転職活動での使用例
転職活動では、応募先企業の理念や業務内容に感銘を受けたことを伝えることで、志望度の高さや意欲をアピールすることができます。
例文:
・御社の「お客様第一主義」という経営理念に強く感銘を受け、ぜひその一員として貢献したいと考えました。
・採用面接でお話しいただいた御社の将来ビジョンに感銘を受け、共に成長したいと思いました。
転職活動では、具体的にどの点に感銘を受けたのかを明確に伝えることで、熱意を効果的に伝えることができます。
「感銘を受ける」を効果的に使うためのポイント
「感銘を受ける」を効果的に使うためには、いくつかのポイントがあります。これらのポイントを押さえることで、言葉の力を最大限に引き出すことができます。
具体的なエピソードを交える
「感銘を受ける」を使う際には、具体的なエピソードを交えることが重要です。抽象的な表現よりも、具体的な事実を交えることで、相手に伝わりやすくなります。
例文:
・御社の社員が自主的に行動し、お客様の問題を迅速に解決したエピソードに感銘を受けました。このような姿勢は、自分自身が目指す理想の働き方と一致しています。
このように、具体的な出来事を交えることで、感銘を受けた理由がより明確になります。
感銘を受けた理由を詳細に説明する
感銘を受けた理由を詳細に説明することで、相手に自分の感動をよりリアルに伝えることができます。
例文:
・社長の講演を通じて、困難な状況でも諦めずに挑戦し続ける姿勢に感銘を受けました。そのお話を聞いて、自分もどんな困難にも立ち向かう勇気を持とうと思いました。
このように、なぜ感銘を受けたのかを具体的に説明することで、相手に自分の気持ちが伝わりやすくなります。
適切な場面で使用する
「感銘を受ける」は強い感動を表す言葉ですので、適切な場面で使用することが重要です。日常的な些細な感動には、他の表現を使うようにしましょう。
例文:
・彼の話し方に感銘を受けました。次回のプレゼンテーションで参考にしたいと思います。
ビジネスや転職活動など、重要な場面で使うことで、その言葉の重みが増します。
「感銘を受ける」の類語や関連表現
「感銘を受ける」の類語
「感銘を受ける」は非常に強い感動を表す言葉ですが、同じような意味を持つ類語もいくつか存在します。これらの類語を知っておくことで、表現の幅が広がります。
感動する
「感動する」は、「感銘を受ける」の最も一般的な類語です。感銘を受けた際の感情を表現するために広く使われています。
例文:
・彼のスピーチに深く感動しました。
・この映画を見て心から感動しました。
心打たれる
「心打たれる」は、感銘を受けるときの心の動きを強調する表現です。
例文:
・彼の真摯な態度に心打たれました。
・その演技に心打たれるものがありました。
印象に残る
「印象に残る」は、感動や感銘を受けたことを記憶に強く留めることを表現します。
例文:
・彼の言葉が非常に印象に残りました。
・その風景は今でも強く印象に残っています。
「感銘を受ける」と関連する表現
「感銘を受ける」に関連する表現も数多くあります。これらの表現を使うことで、感銘を受けた際の具体的な状況や感情をより詳しく伝えることができます。
心に響く
「心に響く」は、感銘を受けた際の深い感動を強調する表現です。
例文:
・彼の言葉が私の心に深く響きました。
・その歌声が心に響き、涙が止まりませんでした。
魂が揺さぶられる
「魂が揺さぶられる」は、非常に強い感動を受けた際の感情を表現する言葉です。
例文:
・彼の演奏に魂が揺さぶられました。
・そのドキュメンタリーを見て魂が揺さぶられる思いでした。
目に焼き付く
「目に焼き付く」は、感動した光景や出来事を強く記憶に留めることを表現します。
例文:
・あの美しい風景が目に焼き付きました。
・その瞬間が今でも目に焼き付いて離れません。
「感銘を受ける」の使い方を広げるための練習
「感銘を受ける」を含む表現を豊かにするためには、日常的に練習することが大切です。具体的な状況を想定しながら、様々な表現を使ってみましょう。
日記を書く
日々の出来事や感じたことを日記に書くことで、自分の感情を言葉にする練習ができます。特に「感銘を受けた」出来事を詳細に書き記すことで、表現力が向上します。
例:
今日は、友人の話を聞いて強く感銘を受けました。彼の挑戦する姿勢に心が揺さぶられ、私ももっと頑張ろうと決意しました。
読書や映画鑑賞後の感想を書く
読んだ本や見た映画の感想を書くことで、感銘を受けたポイントを具体的に表現する練習ができます。
例:
この本の主人公の生き様に深く感銘を受けました。彼が困難に立ち向かう姿は、私に勇気を与えてくれました。
「感銘を受ける」の使い方例文集
さまざまなシチュエーションでの例文集
ここでは、さまざまなシチュエーションでの「感銘を受ける」を使った例文を紹介します。これらの例文を参考にすることで、実際に「感銘を受ける」を使う際のイメージを具体的に掴むことができるでしょう。
個人の経験に基づく例文
個人的な体験や経験に基づいて「感銘を受ける」を使う場合の例文をいくつか見てみましょう。
例文:
・大学時代の恩師の言葉に感銘を受け、私の人生観が大きく変わりました。
・旅行先で出会った人々の温かさに感銘を受け、日本に帰ってからもその思い出が忘れられません。
仕事やキャリアに関する例文
仕事やキャリアにおいて「感銘を受ける」を使う場合の例文です。職場での感動的な出来事や、キャリアの転機となった体験を表現します。
例文:
・新しいプロジェクトに取り組むチームの情熱に感銘を受け、私も一丸となって取り組む決意を新たにしました。
・同僚の自己成長に対する姿勢に感銘を受け、私も自分自身のスキルアップに励むことを誓いました。
教育や学びに関する例文
教育や学びの場で「感銘を受ける」を使う場合の例文です。教師や講師の影響、学びの中で得た感動を表現します。
例文:
・教師が生徒一人一人に向き合う姿勢に感銘を受け、教育の大切さを改めて感じました。
・セミナーでの講師の話に感銘を受け、自分もその道を目指したいと思うようになりました。
文化や芸術に関する例文
文化や芸術作品に触れた際に「感銘を受ける」を使う例文です。映画や音楽、文学などに対する深い感動を表現します。
例文:
・この映画のストーリーに感銘を受け、何度も観返しています。
・コンサートでの演奏に感銘を受け、その音楽が今でも心に響いています。
「感銘を受ける」を活用するための実践練習
これまで紹介した例文を参考に、自分自身の経験や感じたことを「感銘を受ける」を使って表現する練習をしましょう。実際に使ってみることで、自然に言葉が出てくるようになります。
日常的な感動を表現する
日常生活で感じた小さな感動を「感銘を受ける」で表現してみましょう。具体的なエピソードを交えることで、表現力が豊かになります。
例文:
・友人の優しさに感銘を受け、私ももっと人に優しくしようと思いました。
・自然の美しさに感銘を受け、写真を撮り始めました。
自己分析を深める
「感銘を受ける」を使って自己分析を深めることで、自分自身の価値観や考え方を見つめ直すことができます。
例文:
・多くの人々が助け合う姿に感銘を受け、自分も社会に貢献できる仕事を選びたいと思いました。
・過去の失敗から立ち上がる人々の姿に感銘を受け、自分も前向きに挑戦する勇気を持ちました。
まとめ
「感銘を受ける」という表現は、深い感動を伝えるための非常に強力な言葉です。日常生活やビジネスシーン、転職活動など、さまざまな場面で適切に使うことで、自分の感情や考えを効果的に伝えることができます。
具体的なエピソードや理由を交えることで、相手に伝わりやすくなります。日々の生活の中で「感銘を受ける」を使って表現力を磨いていきましょう。
「感銘を受ける」の豆知識
ここからは関連する情報を豆知識としてご紹介します。
語源について
「感銘」という言葉は、中国古代の「肝に銘ずる」という表現が由来とされています。「肝」は心の深い部分を意味し、「銘ずる」は刻み込むという意味です。これが転じて、深く感動し心に刻むことを表すようになりました。
感銘と感動の違い
「感銘を受ける」と「感動する」は似たような意味を持ちますが、ニュアンスに違いがあります。「感銘を受ける」は、深く心に刻まれる感動を表し、長く心に残るものです。一方、「感動する」は一時的な強い感情の動きを表すことが多いです。
感銘を受けると記憶の関係
心理学的には、強い感動を受けた出来事は、記憶に残りやすいと言われています。これを「エモーショナル・メモリー」と呼び、感銘を受けることが記憶の定着に大きく影響します。
日本文学における「感銘」
日本文学の中でも「感銘」をテーマにした作品が多く存在します。例えば、夏目漱石の作品には、登場人物が何かに感銘を受けて人生観が変わる場面がよく描かれています。
ビジネスにおける感銘
ビジネスシーンでは、感銘を受けたことを共有することで、チームのモチベーションを高める効果があります。リーダーシップ研修などでも、感銘を受けた経験を話し合うことで、リーダーの資質を磨くプログラムが取り入れられています。
感銘を受けやすい人の特徴
感銘を受けやすい人は、共感能力が高く、他人の感情や状況に対して敏感に反応する傾向があります。また、好奇心が強く、新しい経験や知識を積極的に受け入れる姿勢があることが多いです。
感銘を受ける場面の作り方
感銘を受けるためには、自分の感性を磨くことが重要です。例えば、芸術作品に触れる機会を増やす、旅行に出かけて新しい文化を体験するなど、感性を刺激する活動を取り入れると良いでしょう。
感銘を表現する英語表現
英語で「感銘を受ける」に相当する表現は “to be deeply impressed” や “to be moved” です。ビジネスシーンでは “to be profoundly influenced” という表現もよく使われます。
感銘を受ける名言
歴史上の偉人たちが残した名言の中には、感銘を受けるものが多く存在します。例えば、マハトマ・ガンジーの「あなたが世界に望む変化に自らがなりなさい」という言葉は、多くの人々に感銘を与えています。
感銘を受ける映画・音楽
感銘を受ける映画や音楽には、心に深く響くストーリーやメッセージが込められています。例えば、映画「ショーシャンクの空に」やベートーベンの「第九交響曲」などは、多くの人々に感銘を与える作品として知られています。
感銘を受けた経験の共有
感銘を受けた経験を他人と共有することは、その感動を再確認し、より深く記憶に刻むことにつながります。また、他人にその感動を伝えることで、共感を得やすくなり、人間関係の構築にも役立ちます。
感銘を受けるためのマインドフルネス
感銘を受ける体験を増やすために、日常生活でのマインドフルネスを実践することが有効です。現在の瞬間に集中し、心を開いて新しい経験や感情を受け入れることで、感銘を受けやすくなります。
これらの豆知識を参考に、「感銘を受ける」という表現の意味や使い方をさらに深く理解し、日常生活やビジネスシーンで効果的に活用していきましょう。
以上、「感銘を受ける」という表現について、その意味や使い方を詳しく解説させていただきました。この言葉は、日常生活やビジネスシーン、そして転職活動において、私たちの感動や深い印象を表現するための非常に強力なツールです。
おわりに
本日お伝えした内容を参考にしていただき、具体的なエピソードや理由を交えながら、この表現を効果的に使ってみてください。また、今回ご紹介した豆知識や類語、対義語も活用して、さらに豊かな表現力を身につけていただければと思います。
皆様が、感動や感銘を他者に伝える際に、この情報が役立つことを願っております。




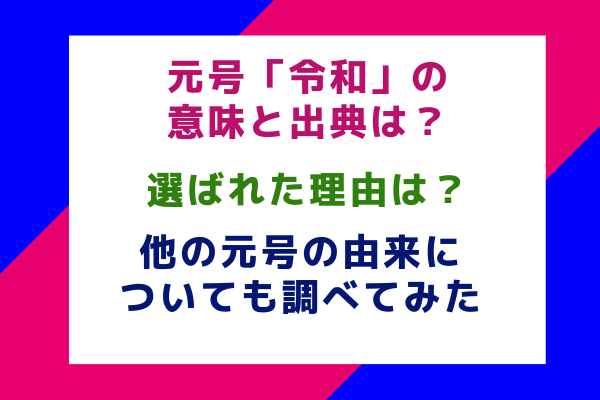



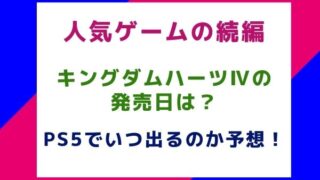
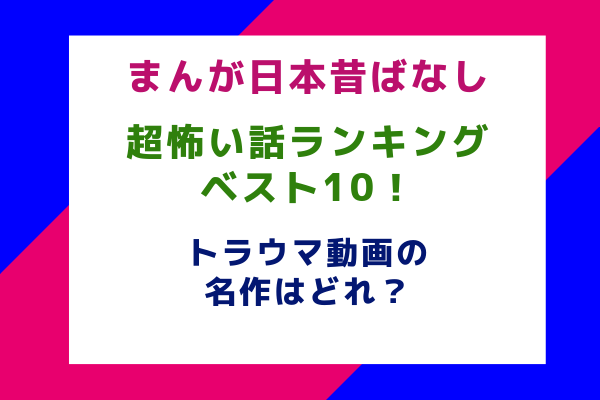










コメント